 みんなの会
みんなの会 みんなの会(10/11)やりました。次回は12月
【テーマは集まり】
いま「居場所」が熱い!
ここ数年居場所ネットワークのシンポジウムに関わったり、周囲でも子ども食堂が盛んであったり、当事場という言葉が出てきたりといろんな地域で大小様々な居場所が、ただ場所という意味以上にその場所を居場...
 みんなの会
みんなの会  みんなの会
みんなの会  みんなの会
みんなの会  イベント開催スケジュール
イベント開催スケジュール  イベント開催スケジュール
イベント開催スケジュール  みんなの会
みんなの会  資格講座開催スケジュール
資格講座開催スケジュール  イベント開催スケジュール
イベント開催スケジュール  イベント開催スケジュール
イベント開催スケジュール 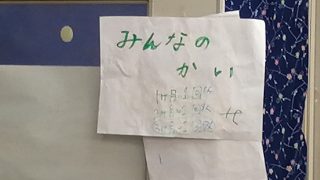 みんなの会
みんなの会